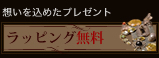-
ブランド一覧
- Gimmel Garden(ギメルガーデン)
- Gimmel Garden ジュエリーコレクション(ギメルガーデンジュエリーコレクション)
- Ana-morphilia(アナモルフィリア)
- 子供と魔法
- hidora(ヒドラ)
- 櫻井結祈子
- optoo(オプトー)
- 江島多規男
- Yoda Hidemi(ヨダヒデミ)
- 外山光男
- Lhiannan:Shee(リアナンシー)
- 植田明志(AKISHI UEDA)
- AKISHI UEDA Drawing Works
- AGU(あぐ)
- エビ
- nyui(ニュイ)
- eerie-eery(イーリーイーリー)
- Mantam(マンタム)
- StellAnalista(ステラナリスタ)
- DECOvienya(デコヴィーニャ)
- ojo(オジョ)
- GREEN-EYED CREATION(グリーンアイドクリエーション)
- 猪野屋牧子
- HiNGE(ヒンジ)
- guide(ガイド)
- V.Sabrina(Vサブリナ)
- armarium(アルマリウム)
- 金﨑遥
- katarito(カタリト)
- 尾崎武秀
- jouer avec moa?(ジュエアヴェックモア)
- クラメンツ商會
- GARARA(ガララ)
- CUTICURA(斧原由季)
- mayu mooja!(マユムージャ)
- TORQUATA(トルクアータ)
- HOASHIYUSUKE(ホアシユウスケ)
- EmiriA(エミリア)
- Sipkaクリスマスセレクション
- Sipkaハロウィンセレクション
- ギフトセレクション
- アイテム
- 海外発送不可
eerie-eery 「鯨と足首座の支配人」
¥29,700
税込
子供の頃、怖いと感じたこと、好奇心を抑えずにはいられなかった記憶などをテーマに
アクセサリーやオブジェ、洋服の製作、イラストやパフォーマンスなど、
幅広いジャンルに渡って表現活動を展開するアーティスト eerie-eery(イーリー・イーリィ)。
eerieによる立体作品、不気味で少しファニーな人形たちは、
作家自身の分身であるかのように物言わず静かに佇んでいます。
個展「追憶と眠りの国 ~眠りの為の回顧展~」用作品。
死の国[ アムニジア ]にひっそりと佇む歯科医院を舞台に繰り広げられる
追憶の物語と、その登場人物たちを人形で表現したシリーズ。
様々な理由で旅立ちを迎えた死者たちを具現化した作品です。

架空の劇団 "鯨と足首座" を舞台にした物語の登場人物
「鯨と足首座の支配人」のその後を表現した作品。
木箱の中に首の無い支配人の人形が入れられています。
個展「追憶と眠りの国 ~眠りの為の回顧展~」と "鯨と足首座" の物語を繋ぐ作品となります。

支配人の人形は固定されておらず、箱の中に入れたままでも
取り出して単体で飾って頂く事も可能です。
人形本体 全長:約15㎝。
木箱 縦:約10㎝。横:約17㎝。高さ:約14㎝。
※こちらの作品は個展「追憶と眠りの国 ~眠りの為の回顧展~」会期終了後
(2014年7月21日)以降の発送となります。
納期についてはご相談下さい。
【 鯨と足首座-支配人の話- 】
支配人が支配人となったのは支配人が誰かに支配人と呼ばれる
ずっと前の事であり支配人が支配人として誰かを支配するずっと前の事であった。
支配人が支配人となる前、支配人は海の近い街に恋人と暮らしていた。
三角の青い屋根が目を引く二階建ての家で、その一階で靴屋を営んでいた。
支配人の恋人は靴職人であったので、恋人が靴を作り、
それを支配人が売るという形で二人は協力して店を切り盛りしていた。
特に儲けるわけでもなく、かといって貧しいわけでもなく、
二人は今日一日分の幸せに感謝して毎日優しく暮らしていた。
麦が実り辺り一面金色の野原になった季節のある日、
少し離れた東の街で、獅子の顔と龍の尾を持つ緑色の竜巻が起きた。
この地方では天気が荒れること自体とても珍しいことであったので、
この前の新月の日に新しく生まれた魔女の仕業ではと囁かれていた。
支配人の住む街も警戒をして過ごし、街の入口の森の木々には護符が貼られた。
その日の夜のことであった。
夜遅くに支配人の家の一階、つまり靴屋の扉を叩く音がした。
魔女を警戒する為、夜中も街の人達が交代で見張りをしていたので
交代の知らせが来たのかと支配人は階段を降りていった。
しかし様子がおかしかった。
なんと家の一階部分は支配人の腰の辺り程まで水に浸かっていたのである。
これはどういう状況だ、夢でも見ているのかと思い、
支配人は階段を引き返し急いで恋人の眠る二階の部屋に戻った。
しかし部屋に戻った支配人には更に唖然とする出来事が待ち受けていた。
二人が寝ていた部屋には得体の知れない緑色の大きな生臭い動物が
ぎちぎちになりながらその巨体を収めていたのである。
頭から潮を吹いたのでそれが鯨だとわかった。
(恋人は、、)
支配人は寝床の辺りを必死に探した。
しかし恋人の姿は無かった。
支配人はすっかり気が動転してどうしていいかわからなくなっていた。
これは悪夢に違いない、早く覚めてくれと何度も神に祈り、
奇声をあげながら恋人を探し回った。
その時であった。
鯨の口の白い髭から足首が覗いているのが目に入ったのである。
それは恋人の足首だった。
支配人の体を絶望感が突き抜けたかと思うとすぐに怒りが駆け巡った。
支配人は一心不乱に足首を引っ張った。
しかし中々抜けず、支配人は怒りにまかせて鯨を殴り、蹴った。
それでも鯨は恋人を離してくれなかった。
支配人は泣きながら足首に抱き着き引っ張り続けた。
すると急に足首を引っ張る感触が軽くなった。
腕の中を見ると恋人の足首が取れていた。
鯨は目を三日月形にしてにやりとすると、
体をくねらせながら後退りして部屋からいなくなった。
同時に、下から風呂の栓を抜いたような水の流れる音がしたので、
一階の水が引いていったのがわかった。
水の吸い込まれる音が消えると辺りは急に静かになった。
支配人は呆然と立ち尽くし、全く状況を理解できずにいた。
鯨は本当に夢のように消えてしまった。恋人も。
(全て夢だったのだろうか。しかし恋人も消えてしまった。
夢に連れていかれたというのだろうか。
そんな馬鹿げた事があるものか。
もしかしたら恋人なんて最初からいなかったのではないか。
一体どこから夢を見ていたというのだろうか。)
支配人は腕の中に視線を落とした。
腕の中には足首があった。
壁には大きな穴が空いていて、そこから綺麗な三日月が見えていた。
夜はとても静かであった。

それから支配人は街を出た。
街を出る前日に、支配人は恋人の葬式をひっそりと行った。
結局体は見つからなかったので、残された足首と恋人の作った靴達を棺に入れた。
靴職人が足首だけになってしまうなんて、こんな皮肉なことがあるだろうか。
街では支配人が恋人を殺したのではないかという噂がたっていた。
それだけでなく、東の街のの緑色の竜巻も支配人の仕業で、
魔女は支配人だと言い張る者も沢山いた。
しかし支配人は寂しくなかった。
心が壊れてしまったのである。
三日程放心状態のまま歩き続け養鶏場の横を通った時、
支配人はルンペンが鶏を盗み出しているところに遭遇した。
ルンペンは鶏の頭を捻ると持っていた斧で頭を落とした。
手際よく血抜きをしていると、ルンペンは支配人に気付きぎょっとした顔をした。
支配人を養鶏場の者と間違えたのか、ルンペンは鶏と斧を放って逃げて行ってしまった。
頭を無くした鶏も、やれ助かったという風にふらふらと走って何処かへ行ってしまった。
支配人は暫くそれらを見送って、残された鶏の頭と斧を前に立ち尽くした。
支配人は鶏の頭を被ってみた。
血の臭いが少々嫌ではあったがすぐになれた。
そしてまだ温かい肉の温度にとても安心した。
支配人の中で何かが生まれようとしていた。
鶏の頭を被り、支配人は知らない何者かになれた気がした。
こうしていれば何も怖くない気さえしてきたのである。
支配人はそれまでの己を捨て新しい顔を手に入れた。
支配人が初めて支配したのは支配人自身であった。

そうして支配人は[鯨と足首座]という劇団を立ち上げ、一人で旅芸人を始めた。
何処で身につけたわけでもない その奇妙な芝居は不思議と体に馴染んでいた。
支配人は人当たりがよく、客からも好かれた。
不定期で場所も疎らに行う公演にも、何処で噂を嗅ぎ付けたのか、
足しげく通う者まで現れる程であった。
さらには弟子入りをしたいと志願する者まで現れた。
しかし支配人は簡単には弟子を取らなかった。
特別な条件があったのである。
何年か経ったある時、支配人は漸く劇団員を四人だけ迎え入れた。
沢山の志願者の中から四人が選ばれたのには訳があった。
その四人にはある奇妙な共通点があったのだ。
それは、[己の顔を捨てた]ということであった。
....................................................................................................................

『 鯨と足首座の支配人 』
支配人は鶏の顔を外し鏡を見た。
(わたしは新しい顔を手に入れ、新しい人生を歩んでいる。
しかし本当にこれがわたしの救われる道であったのだろうか。)
支配人は鯨に食われてしまった恋人のことを思った。
(ごまかしていただけではないのか。
わたしはわたしの運命を受け入れられなかっただけに違いないのだ。)
支配人は斧を手に取ると自分の首に当てた。
(戯曲はもう終わりにしよう。
貴女に逢いたかった。わたしはそれだけだったのだ。
沢山の人を巻き込んで、わたしはもっと早く、この舞台に幕を降ろさねばならなかった。)

支配人は自分の本当の首を切り落とした。
首が軽くなったと同時に今まで背負っていた荷を全て降ろした感覚がした。
こうして支配人による支配人の支配は終わった。
静かな夜だった。
支配人の瞼の裏に漆黒の緞帳が重く垂れ込めた。
意識の途切れない間に支配人は身支度を始めた。
食糧品等の入っていた大きめの箱を持ち出し、
川辺に浮かべるとその中にうずくまり街を後にした。
水のぶつかる音に耳を傾けながら、ふと劇団員達のことを案じた。
川面を照らす月はいつかも見たような三日月であった。

支配人が街を去った後も、彼の立ち上げた劇団は続いていた。
初めのうちは支配人の所在を聞く者が多少なりともいたが、
次第に気にする者はいなくなっていった。
それから暫くして、街のマスク屋で支配人によく似た鶏の仮面が売りに出された。
隣には特に何の変哲もない煤けた茶色の鳥の仮面も並んでいた。
二つの仮面はすぐに買われてしまったようだが、売りに出されている間、
毎日ショーウインドーを見つめる一人の義足の女の姿があったという。