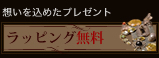-
ブランド一覧
- Gimmel Garden(ギメルガーデン)
- Gimmel Garden ジュエリーコレクション(ギメルガーデンジュエリーコレクション)
- Ana-morphilia(アナモルフィリア)
- 子供と魔法
- hidora(ヒドラ)
- 櫻井結祈子
- optoo(オプトー)
- 江島多規男
- 佐藤麗生(Reo sato)
- ∮TaKu‘ ,n∮
- Chantaku
- SKARNZ
- 外山光男
- Lhiannan:Shee(リアナンシー)
- eerie-eery(イーリーイーリー)
- nyui(ニュイ)
- 猪野屋牧子
- 植田明志(AKISHI UEDA)
- AKISHI UEDA Drawing Works
- AGU(あぐ)
- エビ
- シプカみやげ
- Mantam(マンタム)
- StellAnalista(ステラナリスタ)
- DECOvienya(デコヴィーニャ)
- ojo(オジョ)
- GREEN-EYED CREATION(グリーンアイドクリエーション)
- HiNGE(ヒンジ)
- guide(ガイド)
- V.Sabrina(Vサブリナ)
- armarium(アルマリウム)
- 金﨑遥
- katarito(カタリト)
- 尾崎武秀
- jouer avec moa?(ジュエアヴェックモア)
- GARARA(ガララ)
- CUTICURA(斧原由季)
- クラメンツ商會
- mayu mooja!(マユムージャ)
- TORQUATA(トルクアータ)
- HOASHIYUSUKE(ホアシユウスケ)
- EmiriA(エミリア)
- Sipkaクリスマスセレクション
- Sipkaハロウィンセレクション
- .
- ギフトセレクション
- アイテム
- 海外発送不可
植田明志 「灰色の街のテイテイ図」
¥18,857
税込
「記憶」を媒体とした空間造形から、ある種のノスタルジーを感じさせる世界を表現する作家 植田明志。
無音のような静けさと、理想的な深層心理の核心を探求する、その作品世界は見る者の心に深い余韻を残します。

「灰色の星で」
遥か昔は栄えていて夏でも冬でも煙を吹き出していたらしいのだが。
僕は風の噂で、「色んな種類の夢を犠牲にしすぎたせいだ。」と聞いている。
ここの家はみんな三角形。短いものから長いものまで、沢山。
その理由は街の真ん中に立っている大きな煙突。絶えず黒い煙を吹き出している。
唯一昔の街から今までずっと動いている塔だ。

その膨大な時間たるや、小さな星が生まれて死ぬまでの時間に等しいらしい。
廃墟となった家々に、その煙突からの灰が降り積もって三角形になった、という話だ。
星を見ようとするくらい首を曲げなければその塔の先っちょは見えない。
燃え上がる炎が少し見える。
それはまさに黄昏時を作っている機械のようだ。
それにちなんでここの住人は「ユーヤケ塔」と呼ぶ。
奇しくもここの街は年中夜だから、「ユーヤケ」などの単語も
どこかで本を読んだものから引用してきてあるだけなのだが。

そしてこの時間がやってくる。
ガラガラガラガラ。大きな車輪の音を立てて、遠くで何かが歩いている。
蜃気楼の様に距離感が掴めづらく、正確な大きさは定かではないが、軽くケレスくらいの大きさはありそうだ。
旅人達に僕はいつもこう説明する。
「あれは星を見上げる少年ですよ。触れることも出来なければ近づくこともできない。」

なぜ近づくことも触れることもできないのかと聞き返されることがあるが、僕はわざとらしく聞いていないふりをする。
そしてこう続ける。
「そんなことより、彼らの歌を聴いて下さい。聴こえますか?」
大抵の旅人達は口をポカンと開けて聴き入っているようだった。中には涙を浮かべる人もいる。
僕も昔はそうだった。この時間がたまらなく嫌で、たまらなく待ち遠しかった。
そんな僕達を尻目に、彼らはガラガラガラと、歌を歌いながら闊歩するのだ。
なんでも、この馬鹿に広い星を一周しているらしかった。
姿が見えない時も、誰もいない広大な灰丘の上ですら、彼らはずっと歌っているのだ。

そして過ぎ去った後、決まって旅人はこう口を揃える。
「この街の名前はなんていうんです?」
僕はいつもにやりと笑いながらこう答える。昔の街の名前から因んだと言われる名前だ。
「この街の名前は、トロイメライ。」