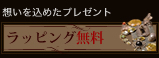-
ブランド一覧
- Gimmel Garden(ギメルガーデン)
- Gimmel Garden ジュエリーコレクション(ギメルガーデンジュエリーコレクション)
- Ana-morphilia(アナモルフィリア)
- 子供と魔法
- hidora(ヒドラ)
- 櫻井結祈子
- optoo(オプトー)
- 江島多規男
- 佐藤麗生(Reo sato)
- ∮TaKu‘ ,n∮
- Chantaku
- SKARNZ
- 外山光男
- Lhiannan:Shee(リアナンシー)
- eerie-eery(イーリーイーリー)
- nyui(ニュイ)
- 猪野屋牧子
- 植田明志(AKISHI UEDA)
- AKISHI UEDA Drawing Works
- AGU(あぐ)
- エビ
- シプカみやげ
- Mantam(マンタム)
- StellAnalista(ステラナリスタ)
- DECOvienya(デコヴィーニャ)
- ojo(オジョ)
- GREEN-EYED CREATION(グリーンアイドクリエーション)
- HiNGE(ヒンジ)
- guide(ガイド)
- V.Sabrina(Vサブリナ)
- armarium(アルマリウム)
- 金﨑遥
- katarito(カタリト)
- 尾崎武秀
- jouer avec moa?(ジュエアヴェックモア)
- GARARA(ガララ)
- CUTICURA(斧原由季)
- クラメンツ商會
- mayu mooja!(マユムージャ)
- TORQUATA(トルクアータ)
- HOASHIYUSUKE(ホアシユウスケ)
- EmiriA(エミリア)
- Sipkaクリスマスセレクション
- Sipkaハロウィンセレクション
- .
- ギフトセレクション
- アイテム
- 海外発送不可
eerie-eery 【「鯨と足首座」の劇団員(囚人)】
¥14,300
税込
子供の頃、怖いと感じたこと、好奇心を抑えずにはいられなかった記憶などをテーマに
アクセサリーやオブジェ、洋服の製作、イラストやパフォーマンスなど、
幅広いジャンルに渡って表現活動を展開するアーティスト eerie-eery(イーリー・イーリィ)。
eerieによる立体作品、不気味で少しファニーな顔の無い人形たちは、
作家自身の分身であるかのように物言わず静かに佇んでいます。

架空の劇団 "鯨と足首座" を舞台にした物語の登場人物を立体化した連作のひとつ。
劇団員のひとり「囚人」のお人形。
鳥のような頭部「囚人の顔」は被り物になっており、取り外しが可能。
取り外すとeerie-eeryの特徴である顔の無いお人形となります。
また別売りの他の劇団員の顔と取り替えが出来るようになっています。
全高:約14㎝。
奥行き:約13㎝(頭頂部からお尻まで)
石粉粘土 布地 レース 藁

"鯨と足首座" の劇団員「囚人の話」
劇団に入ることをゆるされたのはたったの四人で、
若者、病人、囚人、令嬢といった接点のないばらばらの身分の者達だった。
支配人は四人を集めるとこう言った。
「貴方達はこれからこの劇団の劇団員になるにあたり自分の顔を捨ててもらうことになる。
よって今から貴方達の首をこの斧で落とします。」
四人は驚いて顔を見合わせた。
支配人はさらに続けた。

「頭を切り落とすのには理由があります。
そして貴方達を選んだことにもそれに深く結び付く理由があります。
ここにいる皆さんは己の境遇に何かしらの不満を抱いている。
そこで自分の顔を捨て、新しい顔を被り、新しい自分として生きてみては如何だろうかと思うのです。
貴方達は役者になることを望んでここに来たはずです。
ならば演じねばなりません。日頃から己でない何者かを演じればよいのです。
ただそれだけのことです。
そうすればもう誰の目を気にすることもなく生きられるでしょう。」
四人はまた顔を見合わるとゆっくりと頷いた。
「では、そこの木枠に首を置いて下さい。さあさあ。」
四人の足元にはいつのまにか首を置けるように半月型にくり抜かれた木枠が用意されていた。
四人は言われるがままに並べられた木枠に首を置き寝そべった。
「では。」
支配人は斧を高く振り上げるとまず若者の首を落とした。
続いて病人、囚人、令嬢と手際よく落としていった。
その作業はあっという間であった。
四人は頭と体がばらばらになり、前が見えないといった風に頭を探してうろうろし始めた。
「では皆さん、それぞれ好きな頭を選んで被って下さい。それが今日からの貴方の顔です。」
四人はそれぞれに顔を選び被った。

新月の夜に24601は脱獄した。
長い間かけて錆びさせた窓枠を外し牢獄の壁から飛び降りた。
「頼む。生きていてくれ。」
囚人は妹の元へと走った。
月の無い夜の暗闇だけが彼を味方していた。
囚人は妹と二人暮らしであった。
両親は度重なる戦争で既に亡くなっていた。
囚人の家は元々地主の家系でそれなりにいい暮らしをしていたが、
両親が死んでから戦後のどさくさに紛れやってきた親戚家族が
その権利を奪い、さらに二人は家を追い出された。
途方に暮れた二人は両親の形見の時計とネックレスをそれぞれくずしてお金にし、
運河沿いに小さな小屋を建て生活を始めた。
囚人は生活の為に煙突掃除、どぶ浚い、靴磨きなど
たくさんの仕事を掛け持って毎日忙しなく働いていた。
また、追い撃ちをかけるように丁度両親が死んだ頃から妹は謎の病気にかかった。
骨が氷になってしまう病気で他に前例のない奇病として医者にも見放されていた。
囚人は妹を連れいろんな医者の元を回ったがどの医者もお手上げ状態であった。
何年も病院を転々としたお陰でお金も底を尽き、妹は退院を余儀なくされた。
「お兄ちゃんわたしのせいで、ごめんなさい。」
病院からの帰り道、囚人の背中におぶられながら妹は呟いた。
妹はいつも自分責めて謝った。
「お前は何も悪くない。お前は自分自身のこともこの病気のことも憎んではいけないよ。
それに困難な状況の中でわたしとお前の絆をより深めたのはこの病気なのかもしれない。
神様はお前を苦しめるためにこの病気を与えたのではない。
神様は決してお前の敵ではないのだから。」
囚人が妹の方を振り返ると妹は小さく微笑んだ。
囚人の背中にぴったりとくっついた妹の体は柔らかく、氷のように冷たかった。
妹にはそう言いながらも囚人は病気を憎み神を憎んでいた。
(何故妹だけこんな目に遭うのだ。神は何故我々ばかりをこうも見放すのだ。
我々を不幸にした戦争と全ての人間が憎い。恵まれた幸福な家庭が憎い。みんな死んでしまえ。)
囚人の心は憎悪で膨らみ悪魔のそれとなっていた。

他人はあてにならないと、囚人は妹の病気を治すために労働の傍ら独学で医学を学び始めた。
僅かな稼ぎで毎月一冊ずつ医学書を買った。
大学の講義にも忍び込んで参加した。
そんなある日のことであった。
その日も囚人は医学書を買いに古本屋に来ていた。
手に取った古本をレジに持って行く途中囚人の腕を引く男がいた。
「お前俺の金を盗んだろ。」
囚人はこの男は何を言い出すんだといった感じに驚 いた。
「なんなんですか?わたしは今この本を本棚から出してレジに運ぶ最中で
貴方の存在なんて声をかけられる今の今まで気付きもしませんでしたよ。」
しかしその男は引き下がらずに喚き始めたので揉め事かと店の周りには野次馬も集まりだした。
すると野次馬の中から女が進み出てきてこう言った。
「わたし、この人がその旦那のポケットから金をくすんで本に挟むのを見たわ。」
これには囚人も青ざめ驚いた。
「そんなはずはない!わたしはそんなことはしていないし、貴女も何故そのような嘘をつくのだ!」
男は囚人に近寄ると本を指差した。
「ならばその本を見せてみろ。
お前の言うことが正しいのなら俺から盗んだ金はそこに挟まっていないはずだ。」
囚人は
「勿論。」
と本を差し出しページをめくって見せた。
するとどうしたことだろうか、ページの隙間から一枚の紙幣が現れたではないか。
「ほらみたことか!盗人め!」
男は囚人の胸倉を掴み殴り掛かる体勢になった。
囚人は困惑した。
「なにかの間違いだ!わたしはやっていない!」
程なくして騒ぎを聞き付け警官がやってきた。
囚人は警官に訴えた。
「お願いだ、信じてください。わたしはやっておりません!」
しかし警官は聞こうとはしなかった。
囚人は縄で繋がれ連れていかれた。
人混みを抜ける際に先程の男と女が寄り添って笑っていた。
(くそ!グルだったのか。最初からそのつもりだったんだな。やられた!)
囚人は悔しくて泣いた。そして何も知らずに家で待っている妹のことを心 配した。
囚人が連れていかれるのを見送りながら芝居をうった男と女は呟いた。
「やっと復讐ができた。我々を苦しめた奴らは地獄に堕ちればいいのだ。」
この男と女。実は昔囚人の一族に土地を奪われた一族の者であった。
全く皮肉なものである。
人の憎悪のなんと醜いことか。

それから囚人は無実の罪で牢獄で過ごすことになった。
いくらこの身が無実と嘆いても誰も聞かなかった。
しかしこのまま大人しく刑期を全うする事は囚人には耐え難い事であった。
病気の妹を一人にして置いて来てしまったのだ。
食べ物を持ち帰らねば、早く治さなければ、わたしが早く医学を学んで早く処置してやらねば、
妹は死んでしまう。
囚人はすぐに脱獄の計画を立て始めた。
囚人は夜の闇を走り続けやがて街に辿り着いた。
辺りは薄明るくなり朝が近付いていた。
囚人は妹の居る我が家へと急いだ。
運河の脇に二人の過ごしたその小屋はあった。
囚人は駆け寄り勢いよく扉を開けた。
しかしそこに妹の姿は無かった。
囚人は妹の寝ているはずのベッドへ近付き布団をめくった。
布団には人型の形に染みが出来ていた。
妹の体は本当に氷だったのだ。
妹は解けてしまった。
「何故です。神様、貴方はわたしから妹も奪うのですか。
神様、わたしは貴方を憎みます。もうなにも信じない。
皆地獄へ落ちろ。火に焼かれ燃え尽きてしまえ。」
囚人の心は悲しみと憎しみに支配され、ついには悪魔となった。
それから囚人は闇に紛れて人を殺して歩いた。
この世の罪人を裁くのは囚人であった。
そんなある日囚人は街角で妙な劇を目にする。
それが支配人の劇であった。
妙な演目を演じる支配人の目に、囚人は何か自分と似たものを感じた。
(何故惹かれるのかはわからないが。まあしかし気に入らなければ裁けば(殺せば)よい。)
囚人は支配人の劇団に興味を持ち、近付く事にした。

囚人は令嬢の首を被った。
女の肉の柔らかさに驚き、そして何処か懐かしさを覚えた。
それは、きっと妹だった。
背中にあたる妹の柔らかい頬を思い出したような気がした。
しかし囚人には既にそれがなんなのかよくわからなくなってしまっていた。
彼の元にはもう氷のように冷たく固くなってしまった心と
胸に焼き付いた24601という番号しか残されていなかったのである。