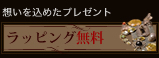-
ブランド一覧
- Gimmel Garden(ギメルガーデン)
- Gimmel Garden ジュエリーコレクション(ギメルガーデンジュエリーコレクション)
- Ana-morphilia(アナモルフィリア)
- 子供と魔法
- hidora(ヒドラ)
- 櫻井結祈子
- optoo(オプトー)
- 江島多規男
- 佐藤麗生(Reo sato)
- ∮TaKu‘ ,n∮
- Chantaku
- SKARNZ
- 外山光男
- Lhiannan:Shee(リアナンシー)
- eerie-eery(イーリーイーリー)
- nyui(ニュイ)
- 猪野屋牧子
- 植田明志(AKISHI UEDA)
- AKISHI UEDA Drawing Works
- AGU(あぐ)
- エビ
- シプカみやげ
- Mantam(マンタム)
- StellAnalista(ステラナリスタ)
- DECOvienya(デコヴィーニャ)
- ojo(オジョ)
- GREEN-EYED CREATION(グリーンアイドクリエーション)
- HiNGE(ヒンジ)
- guide(ガイド)
- V.Sabrina(Vサブリナ)
- armarium(アルマリウム)
- 金﨑遥
- katarito(カタリト)
- 尾崎武秀
- jouer avec moa?(ジュエアヴェックモア)
- GARARA(ガララ)
- CUTICURA(斧原由季)
- クラメンツ商會
- mayu mooja!(マユムージャ)
- TORQUATA(トルクアータ)
- HOASHIYUSUKE(ホアシユウスケ)
- EmiriA(エミリア)
- Sipkaクリスマスセレクション
- Sipkaハロウィンセレクション
- .
- ギフトセレクション
- アイテム
- 海外発送不可
植田明志 「虹の人」
¥605,000
税込
「記憶」を媒体とした空間造形から、
ある種のノスタルジーを感じさせる世界を表現する造形作家 植田明志(うえだあきし)。
無音のような静けさと、理想的な深層心理の核心を探求する、
その作品世界は見る者の心に深い余韻を残します。

個展「虹の跡」用作品。
「虹の人」と題されたオブジェ。
様々な記憶の色の集合である"虹” 。
そして、その時、その場所に自分が確かに存在していたという証である"跡"
をコンセプトにした大型作品です。

幾重にも積み重なった街で形作られた身体。
風化し朽ちかけた遺跡を想わせる身体の各部には
植物が根をはり、胸部と腹部には"爪痕”を想わせる大きな穴があいています。

石粉粘土。
全高:約99㎝(台座部分含む)。
台座底面:最長約44㎝。
※こちらの作品は、植田明志個展「虹の跡」会期終了後(2016年11月16日)のお渡しとなります。
※こちらの作品はラッピング対象外となっております。

「虹の人」
その瞬間、僕は、虹をみた。
その虹はただ、そこに居た。
光と色が交差する。
この降り積もった記憶の山のてっぺんで、僕を待っていた。
地面はふわふわとした — 子供の頃に摘んで誰かにあげた花に、よく似ている。
— 真っ白い花に覆われて、足をくすぐった。
花の下の地面には、たくさんの足跡があった。

僕は、この物語を知っていたよ。
沢山の跡をつけて。
僕は、確かにそこに居たんだよ。
涙は、音のない夕立のように、止めどなく流れ続けた。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
いつからかこの山を歩いていた。
多分、そうだ。山に詳しい友人に、聞いたのだと思う。
その山では、雨が降らなくても虹が見えると、教えてくれたのだ。
「虹って、ふと現れて、消えていくだろう?
でも、心に残るんだ。俺は、それを不思議だと感じるんだ。」
確か、そんなことを言っていた気がする。
何故か、どうしても顔は思い出せなかったが、ロマンチックなやつだ。

思えば、もうしばらく、虹を見ていなかった。
雨が降れば、外には出なくなったし、
コンクリートに染み込んだ、夕立の匂いも嗅がなくなった。
そもそも、子供の頃も、あまり虹を見た覚えはなかった。
ずっと部屋の隅で、様々な色のクレヨンで、何か描いていた気がする。何を描いていたっけ?
気づくと、何時しかあたりは真っ黒になり、空に浮かぶ月も頼りなかった。
山肌は、不規則にぼこぼことしていたが、それなりに舗装されており、
歩いてきた道を見ると、たくさんの足跡があった。
とても大きな動物のもの。
子供のもの。
そして、僕の足跡は、そのどれかに混ざってわからなくなっていた。
僕は、何時からここにいるのか、わからなくなっていた。
どうやったら、そこに居たことにになるのか、術を知らなかった。
僕は、自分の足跡の形すら、覚えていなかった。
この山では、たびたび、不思議なことが起こった。
歩いているうち、たまに、ふっと気配を感じて、暗い崖のほうへ目をやると、子供がいるのだ。
その子供たちは例外なく、奈落の闇にぽっかりと頭だけをだした、
どうやってもそこには辿りつけないような岩の上にいた。
彼らは、本当に小さく、ささやくような声で、歌っていた。
僕が声をかけても、何の反応もしなかった。
きっと、彼らの世界には、僕はいないのだと、思った。

山の中腹あたりに差し掛かると、街が見えた。
その街は、ずっと燃えていた。きっと夕焼けがあそこで眠っているのだ。
僕の家も、燃えているのが見えた。多分、あれだと思う。
山の飛行機が、その街に落ちていくのが見えた。
飛行機は、燃え尽きる瞬間に、流星になれた。
夕焼けは、大きな生き物となって、世界を燃やし尽くしてしまってしまうのだと思った。
そしていつしか、さらに大きな夜が、そんな世界を飲み込んでしまうのだ。

世界は、真っ暗になって、夜の優しさに気付くのだろう。
ふと夜空を見上げると、月が山肌に、さなぎみたいにくっついて眠っていた。
そういえば、僕は約束をしていたことを思い出した。
誰かと会う約束だった。この山の頂上で。
僕は走った。夏が終わったばかりの山は、肌寒かった。
途中で、公園が見えた。遊具はみな闇の中で、怪獣の骨みたいな体を、白く光らせて眠っていた。
怪獣の骨にはたくさんの子供たちが遊んでいた。
まるで、獲物に群がるたくさんの蟻のようだった。
息が切れる。
山はますます黒々としていった。
山肌には様々な種類の鉱石がむき出しになっているらしく、星みたいにきらきら光った。
まるで、宇宙の彼方を走っているようだった。
心臓が張り裂けそうなくらいの全力疾走。
星が、次々と流れていく。この暗闇は、僕をどこへ連れて行ってくれるのだろう。
たまに突き出た星たちで、体を少しずつ切った。
生暖かい感触が伝わる。少し深い傷もあるようだった。
頂上に着いたときには、すっかり月のさなぎはからっぽになっていた。
きっとさなぎの中の海は、宇宙に還っていったのだと思った。
今頃、さなぎの下ではその外皮で作る舟のために、たくさんの舟人で溢れているだろう。
山のここは、真っ白だった。きっと、地面から無数に生えている白いぽわぽわした植物のせいだ。
それに、風に吹かれなかった植物の綿毛が、埃のように真っ白に地面を覆っていた。
下のほうが、少し茶色く、複雑に濁っているのも見えた。

声が聞こえて、振り向くと、君がいた。
何か小さく呟いた。それきり、何も話さなくなった。
二人で、地面に寝転んで、星空をみた。星座を教えようとしたが、
僕の知ってる星の位置とは、少しずつ違っていた。
僕が声をかけようと横を見ると、彼女は真っ白になっていた。
彼女の身体からは無数の白い植物が、空にむかって生えていて、人の輪郭を失っていた。
鉱石に引っ掛かってできた傷も、白くぽわぽわしていた。

僕はどうしようなく泣きたくなった。
泣いてしまえば、きっと楽なのに、鼻が冬の朝のように、少しツンとするだけだった。
涙を堪えようと、地面に顔を伏せた。綿毛がふわふわと迎えてくれた。
ふと、綿毛の隙間に何かが見えた。はっとした。
無我夢中で、降り積もった埃振りを払う。
見えたのは、無数の足跡。
はっとしたその瞬間には、もう涙は溢れていた。
闇の中でひとりぼっちの怪獣のように、わんわん泣いた。

夕立ちみたいな涙のせいで、景色は夏のプールの様に光り輝いて、揺らめいていた。
地面は様々な色が重なりあっていた。
それは、全部僕が知っている色だった。
僕だけが、知っている色だった。
揺らめく景色のせいで、様々な色が複雑に絡まり合った。
その瞬間、僕は、虹をみた。