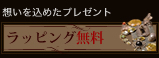-
ブランド一覧
- Gimmel Garden(ギメルガーデン)
- Gimmel Garden ジュエリーコレクション(ギメルガーデンジュエリーコレクション)
- Ana-morphilia(アナモルフィリア)
- 子供と魔法
- hidora(ヒドラ)
- 櫻井結祈子
- optoo(オプトー)
- 江島多規男
- 佐藤麗生(Reo sato)
- ∮TaKu‘ ,n∮
- Chantaku
- SKARNZ
- 外山光男
- Lhiannan:Shee(リアナンシー)
- eerie-eery(イーリーイーリー)
- nyui(ニュイ)
- 猪野屋牧子
- 植田明志(AKISHI UEDA)
- AKISHI UEDA Drawing Works
- AGU(あぐ)
- エビ
- シプカみやげ
- Mantam(マンタム)
- StellAnalista(ステラナリスタ)
- DECOvienya(デコヴィーニャ)
- ojo(オジョ)
- GREEN-EYED CREATION(グリーンアイドクリエーション)
- HiNGE(ヒンジ)
- guide(ガイド)
- V.Sabrina(Vサブリナ)
- armarium(アルマリウム)
- 金﨑遥
- katarito(カタリト)
- 尾崎武秀
- jouer avec moa?(ジュエアヴェックモア)
- GARARA(ガララ)
- CUTICURA(斧原由季)
- クラメンツ商會
- mayu mooja!(マユムージャ)
- TORQUATA(トルクアータ)
- HOASHIYUSUKE(ホアシユウスケ)
- EmiriA(エミリア)
- Sipkaクリスマスセレクション
- Sipkaハロウィンセレクション
- .
- ギフトセレクション
- アイテム
- 海外発送不可
植田明志 「星を繋ぐ王さま」
¥440,000
税込
「記憶」を媒体とした空間造形から、
ある種のノスタルジーを感じさせる世界を表現する造形作家 植田明志(うえだあきし)。
無音のような静けさと、理想的な深層心理の核心を探求する、
その作品世界は見る者の心に深い余韻を残します。

個展「虹の跡」用作品。
「星を繋ぐ王さま」と題されたオブジェ。
インドゾウの頭骨からインスピレーションを得て造形された姿は
長い2本の牙と、エキゾチックな身体の模様が特徴的です。

ふたつの手が繋ぎ合わさったような身体をした「星を繋ぐ王さま」。
惹かれ合う二人は、ふたつでひとつの存在。
王さまの下半身を構成する手は、寂しくて膝を抱えたような姿をしており
もう一方の上半身から伸びた手が、優しく包み込んでいます。

石粉粘土。
全長:約73㎝(牙の先から本体最後部まで)。
高さ:約46㎝。
幅:約22㎝。
※こちらの作品は、植田明志個展「虹の跡」会期終了後(2016年11月16日)のお渡しとなります。
※こちらの作品はラッピング対象外となっております。

こんなに深い夜の中、砂場で子どもたちが二人で遊んでいた。
その砂場はきらきらと金色に輝いているように見えた。
月明かりのせいかと思ったが、夜空に月は浮かんでいなかった。
二人は何かひそひそと話しながら、砂を細く、月のない夜空に伸ばしていった。
彼らのとなりには、古ぼけたプラスチックのシャベルと、
誰かの名前がかかれたバケツが置いてあった。
その名前は、すり減って読めなかった。

数本の砂の塔ができた。
砂を固めた水のせいか、より金色がちらちらと輝いていた。
それはまるで王冠のようにみえた。
どこか遠い宇宙で、ひとつの星が、仲間外れにされた星を呼んだ。
仲間外れにされた星は、誰にも見つけてもらえていない、
ハッブル宇宙望遠鏡にすらも写っていなかった。
太陽ができるずっと前から、この世の隅っこにいた星。
膝を抱えた腕は、深い闇の中で白く震えていた。

名前を呼ばれたとき、もっと震えた。
大木が風に吹かれたような、綺麗な震えだった。
そっと暗闇に腕を伸ばす。指先が触れた。思わず引っ込めた。もう一度、伸ばす。
もうひとつの手が、震えていた星の手を、探るように、確かめるように、握った。
懐かしい感触だった。
懐かしさなんてあるはずない。なのに、いつか会ったことがあるように思えた。
暖かい。いつかの夏の終わりの、温度。
確かな鼓動があった。このリズムも、知っている。
ふたつは少しだけ笑った。涙が流れた。

曖昧な記憶達は涙とまじり合い、光り合った。
それは確かな光になり、ひとつの大きな星になった。
いつしか、あの砂場のふたりはいなくなっていた。
後には、何かを祝福するように、金色に光り続ける王冠があるだけだった。
いつまでも、光っていそうな、微笑み合っていそうな、輝きだった。