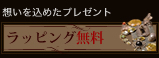-
ブランド一覧
- Gimmel Garden(ギメルガーデン)
- Gimmel Garden ジュエリーコレクション(ギメルガーデンジュエリーコレクション)
- Ana-morphilia(アナモルフィリア)
- 子供と魔法
- hidora(ヒドラ)
- 櫻井結祈子
- optoo(オプトー)
- 江島多規男
- 佐藤麗生(Reo sato)
- ∮TaKu‘ ,n∮
- Chantaku
- SKARNZ
- 外山光男
- Lhiannan:Shee(リアナンシー)
- eerie-eery(イーリーイーリー)
- nyui(ニュイ)
- 猪野屋牧子
- 植田明志(AKISHI UEDA)
- AKISHI UEDA Drawing Works
- AGU(あぐ)
- エビ
- シプカみやげ
- Mantam(マンタム)
- StellAnalista(ステラナリスタ)
- DECOvienya(デコヴィーニャ)
- ojo(オジョ)
- GREEN-EYED CREATION(グリーンアイドクリエーション)
- HiNGE(ヒンジ)
- guide(ガイド)
- V.Sabrina(Vサブリナ)
- armarium(アルマリウム)
- 金﨑遥
- katarito(カタリト)
- 尾崎武秀
- jouer avec moa?(ジュエアヴェックモア)
- GARARA(ガララ)
- CUTICURA(斧原由季)
- クラメンツ商會
- mayu mooja!(マユムージャ)
- TORQUATA(トルクアータ)
- HOASHIYUSUKE(ホアシユウスケ)
- EmiriA(エミリア)
- Sipkaクリスマスセレクション
- Sipkaハロウィンセレクション
- .
- ギフトセレクション
- アイテム
- 海外発送不可
植田明志 「歩くのをやめた夜」
¥88,000
税込
「記憶」を媒体とした空間造形から、
ある種のノスタルジーを感じさせる世界を表現する造形作家 植田明志(うえだあきし)。
無音のような静けさと、理想的な深層心理の核心を探求する、
その作品世界は見る者の心に深い余韻を残します。

個展「虹の跡」用作品。
「歩くのをやめた夜」と題されたオブジェ。
植田明志作品の特徴である老人の顔に
夜の闇を想わせる獣のような身体が造形されています。
死を迎え、その身体は朽ちてしまっても、
その後には、"かつて自分が確かにそこに存在した証” である
キラキラした跡が残るという想いを表現した作品です。

長い時を生き、やがて来る死期を迎えるばかりとなった夜の存在。
黒い毛に覆われたその身体は、深い夜を纏ったかのようです。
やがて、死を迎えたその身体からは夜が抜け落ちていき、骨だけとなり
キラキラとした跡だけが残ります。

石粉粘土。アクリル彩色。
全長:約24㎝。
横幅 最大:約17㎝。(尻尾部分含む)
高さ:約12㎝
※こちらの作品はラッピング対象外となっております。

「歩くのをやめた夜」
もう、私の身体は朽ち始めていた。
ゆっくりと腰を下ろす。もう、歩く意味もなかった。
私はずっとこの夜の中を生きてきた。
真っ暗だったが、それなりに楽しいこともあった。
仲のいいやつもいた。私より先に死んでしまったけど。
もう、私のことを知っているやつは居ないだろう。
それほど、長く生きた。
月はぽっかりと夜空に穴をあけたように浮いている。
あの穴を覗けば、私はずっと昔のことまで思い出せる気がした。
でも、あの穴は私には眩しすぎる。

気づけば、私の目の前に子どもが居た。
私はもう声さえ出なくなっていたし、手足はすでに固まり初めていた。
子どもは何も言わずに、私のひげの中を出たり入ったりしていると思えば、
しとしとと背中に這い上がり、むき出し始めた私の骨をみているようだった。

私はひとりで死にたい。はやくどこかへ行ってくれないか。
そう言いたかったが、声は出ない。
しばらくして子どもは自分の角をぴかぴか光らせながら、
自分のおでこと私の鼻をぴったりとくっつけた。
それは柔らかくて、きっと太陽に照らされた雲はこんなふうに暖かいのだろうと思った。
瞼の裏側が、夏の夕日みたいに滲んだ。
眩しかった。その光はだんだん収束して、あの月のように丸くなった。

もう目も開かなくなっていた。あの子供の顔も見えない。
あの子供の頭を撫でてあげたかったが、手足も動かない。
まだそこにいるのか?
また鼻にやわらかい雲が押し当てられた。

もう、涙が私の瞼一面に広がるのがわかった。
それは夜雨にできる水たまりのように美しかった。
ずっとそばに居てほしいと思った。ああ、どこへも行かないでくれ。

あの子がそばにいるのを感じる。
涙がついに流れた。
暖かい光はぼやぼやとしながら、急激に成長する単細胞生物みたいに私を包み込んだ。
夜が、その光とひとつになったその後には、
月に照らされてきらきらと輝く骨が、いつまでも残っていた。